
|
岩手県内で天然記念物に指定されている多くは巨木・珍木の類です
が、樹木の化石が天然記念物に指定されているものもあります。国の
特別天然記念物に指定されている一戸町の「根反の大珪化木」がそう
です。その一帯では珪化木が多く見られ、「姉帯・小鳥谷・根反の珪化
木地帯」として、地域一帯が国の天然記念物の指定を受けています。
また奥州市江刺区には、岩手県が天然記念物に指定している「藤里
の硅化木」があります。これも同じように、樹木が化石になったものです。
市町村が指定するものとしては、久慈市が指定する「琥珀大原石」があ
ります。これは樹木の化石ではありませんが、樹木が出す樹脂部分が
化石となったもので、いわゆる「コハク」です。
「化石」といえば、枯れた、生気を失った、味気ない……そういうもの
の代名詞のようにも使われます。でもそれら化石1つ1つは、紛れのな
い過去の事実を示すものであり、そこには物語が秘められています。
その多くはロマンに満ちています。それらが生存していた頃の姿や生
態の模様、周りの環境、生存競争、そして進化のドラマ、そんなことを
人々に想像させてくれるのです。
そんな思いで、2つの珪化木をめぐってみました。 |
|
|
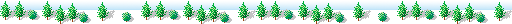 |
|
 |
国指定の特別天然記念物
所在地 一戸町根反字川向 |
一戸町地内の国道4号線から地名の「根反」をあてに、根反川沿いに車を走らせ、どこかどこかと
きょろきょろしながら、ついに探し当てました。木の幹がそっくり石になってしまうというのも不思議で
すが、こんなに太いものがよくそっくり立ち姿で残ったものです。地下に埋っている部分はどうなって
いるんでしょうね。解説によると、スギの一種のセコイアに近い種類となっていますが、セコイアメス
ギだろうというのが一般的です。
直径2メートルといえば結構な大木ですが、かつてこの地盤の上には、このような巨木が立ち並ん
でいたということですねえ。もちろん森の中にはいろいろな動物たちが動き回っていたことでしょう。火
山灰に埋もれたといいますから、火山活動も活発だったことでしょう。1700万年前という気の遠くなる
ような昔の話ですが、地殻変動による移動を受けながら、現在この地でその化石を見せているわけ
す。タイムマシンのカプセルにでも乗って、当時の姿を眺めてみたいものです。
人類の誕生は約300万年前のことで、日本列島に人類がうつり住むようになったのは約60万年前の
ことといいますから、この珪化木がいかに古い時代のものであるか推察できます。近くには縄文遺跡
で知られる御所野遺跡がありますが、縄文時代中期ということで、それはせいぜい4千年程前の話。
この珪化木の前では、それは一瞬前のことだったことになります。なお御所野遺跡から出土した石器
のやじりの中には、珪化木で作られたものも数多く発見されています。一帯には珪化木が多く見られ、
剥離しやすいことから、石器の加工に向いていたと思われます
|
|
 |
|
|
(案内板より) 国指定特別天然記念物 根反(ねそり)の大珪化木
指定年月日 昭和11年12月16日(天然記念物指定)
昭和27年3月29日 (特別天然記念物指定)
所 在 地 一戸町根反字川向
所 有 者 地蔵堂 政志
この珪化木は直立していた木が、火山灰に埋もれてできた現地性の珪化木です。
大きさは直径2メートル・高さ6.4メートル・目通り幹周囲約7メートルで、直立する珪化木と
しては日本最大のものといわれています。
樹種はスギの一種で、現在北米太平洋沿岸にわずかに自生しているセコイアに近い種類
と考えられます。
珪化木とは、木の組織に珪酸分がとけて入り、蛋白石(たんぱくせき)あるいは瑪瑙(めのう)
化して、木の組織と置きかわったものです。珪化木の含まれている地層は、新第三系の四ッ役
層という今から約1700万年前のもので、この地層の中で長い時間かかって珪化したものです。
一戸町の根反川・平糠川・馬淵川の河床には、このような珪化木が多量に含まれており、珪
化木地帯として、国の天然記念物に指定されていますが、中でもこの珪化木は特に貴重であり、
国の特別天然記念物に指定されています。
平成13年3月20日 一戸町教育委員会
|
|
|
 |
|
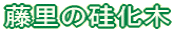 |
岩手県指定の天然記念物
所在地 奥州市江刺区藤里字石名田乙 |
|
|
| 愛宕山と呼ばれる丘の上に愛宕神社があって…… |
|
|
|
天然記念物に指定されて珪化木ということでは、奥州市江刺区藤里に岩手県が指定する
「藤里の硅化木」があります。そこも訪れてみました。ちなみにここでの珪化木は「硅化木」
の字が使われています。
探し当てた現地・愛宕山一帯は、稲瀬層(新第三系中新統)という安山岩をまじえた砂質凝
灰岩から成っているそうで、ここにはかつては城もあったと地元案内板は伝えています。めざ
す珪化木は愛宕山の一番高いところにある愛宕神社に登って、その脇から少し下った崖の斜
面にありました。金網が邪魔してうまく写真が撮れませんが、「文化財」としての珪化木を保護
する上では止むを得ないでしょう。
現地での珪化木の説明は簡単なもので、1200万年以前のセコイアメスギが硅化したもので
あること、高さ3.5メートル、直径1.35メートル、天然記念物の指定は昭和38年12月という
ことだけです。他の解説書などによると、この様子から埋没する部分を判断すると全長は
10メートルを越すだろうと見られています。この珪化木は岩手県内では根反の大珪化木に
次いで大きく、しかも直立した樹幹であることが珍しく、珪化木の少ない県南地方としては
貴重なものとされています。 |
|
 |
|
|
「セコイアメスギ」についての豆知識
「根反の大珪化木」と「藤里の硅化木」の元になっているセコイアメスギ。白亜紀から第三期にかけ
て、北半球で広く繁茂したことがその遺体などから確認されています。日本の鮮新世ころの地層から
も、これらの遺体が広く知られているとのことです。現在は北アメリカ・オレゴン州からカリフォルニア
州の太平洋に面した山地に自生して、いわゆる巨木地帯の主要構成樹種の1つになっています。セコ
イアというと一般にセコイアメスギのことをいい、高さ100m、直径8mにもなり、高いのは112mも記録
され、世界で最も丈の高い裸子植物です。スギ科の常緑高木で、葉がイチイに似ていることから、イチ
イモドキという名もついています。
一方同じく北アメリカのシェラ・ネバダ山脈西側の標高の高い山地には、セコイアオスギともいわれる
セコイアデンドロンが分布しています。こちらの方は直径が11mにも達し、2000〜4000年も生き、世界
で最も長寿で、体積も大きい裸子植物とされています。
セコイアは生長が早く、他の針葉樹と異なり、木を伐採した後の切り株から多数の芽を出す性質をも
っています。いわゆる「ひこばえ」です。現在では世界各地で植栽され、日本でも関東以西のあたたか
い地域で庭園や公園に植えられています。しかしセコイアデンドロンの方は病害などのためほとんど
生育できません。
セコイア類は樹皮が厚く、60cmにもなるそうです。そのため山火事があっても樹皮に火傷するだけで
命に別条なく、かえって火事のストレスで、充実した種子が生産されるといいますから驚くばかりです。
セコイアと混生していた広葉樹は樹皮が薄いので、頻繁な火事にあうと枯れてしまい、その跡には元気
のいいセコイアの若木が生長していきます。こうして長い年月をかけて、セコイアの純林ができていくと
いうわけです。セコイアは山火事がないと広葉樹に負けて種の維持ができないわけですから、セコイア
にとっては山火事は歓迎だったわけです。もの言わぬこの珪化木も、調べてみると、生きていた頃はこ
んな秘めた特技をもっていたんですねえ。
なお、生きている化石として有名なメタセコイアは中国の奥地で発見されましたが、植物分類上は同じ
スギ科でも別属です。セコイアに似ているとうことでメタセコイアと名づけられていますが、こちらの方は
落葉性です。 |
|
 |
|
|
|